浴槽につかる私。窓を開ける。網戸越しに雲が見える。空、田んぼ、道路、通り過ぎる車。
浴槽につかる私は、風呂場の壁や花瓶に生けられた花を、ぼーっと見る。ぼーっと見て、外を走る車の音に注目する。
車がどちらから走ってきているのかを当てようとしてみる。
車がこちらに走ってくる音はだんだん大きくなってくるが、私がいる風呂の近くに来るまで、どちらから走ってくるか分からない。直前まで、分からない。風呂の中にいるので、音が反響してなおさら音源を特定するのが難しい気がする。それでも集中して、車がどちらから走ってきているのかをあてようとしてみる。なかなか難しい。
フクロウの耳の位置は、左右対称ではないそうだ。獲物の位置を立体的に捉えるためだそうだ。
人間の耳もフクロウほど高性能ではないかもしれないが、音がどの辺から発生しているかをある程度特定することはできると思う。では音の大きさや音源と自分の距離など、どのくらいの条件になれば音源を特定できるのだろうか。そう思って、浴槽につかる私は走り来る車のタイヤの音に耳を傾けていた。
結論と言えるほどの収穫はなかったが、分かったこと。3段階に分けられそうだということだ。つまり、車の位置が分からない段階、多分こっちかなという段階、確信した段階である。初めの段階は、車の音の聞こえ始めと対応しており、小さな音、まだ遠いところに車がいる。二番目の段階は中くらいの音量やや近い距離に車は近づいてきているが、聞こえ方は漠然としているというかぼーっとした音という感じであり、多分こちらから聞こえてくる、というような感じである。この段階になればどちらから車が来ているかを予想できる。しかし予想が必ずしも当たるとは限らない段階である。最後の段階は、車の音が大きく距離も近いため、どちらから来ているのかをはっきりとイメージすることができる段階である。音の変化をよりはっきりと感じることができ、今どの辺を走っているのかを思い浮かべることができる。なおこの3段階ははっきりと段階に分けられるというよりは、グラデーション的な感じである。だから第1段階と第2段階がはっきり区別できる、というよりも、重なっている部分があって、明確に分けられない、あいまいである、といった感じである。
車の音に注目したが、電車においても似たようなことがあるかもしれない。というのも、私はときどき踏切がおりてどちらから電車が来るかを予想することがある。これは、個人的には車よりも当てるのが難しいと思う。少なくともこれまで私が遭遇した踏切においては。あくまでも聴覚だけで方向をあてようとする場合街中の音、踏切のなる音、車の音、風の音、ラジオの音など、いろいろな音があるから難しいと思う。まあ、そんなかんじ。
それにしても、聴覚というのはよくできた仕組みだなと思う。
おわり。

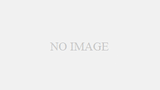
コメント